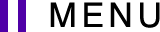急須で淹れる茶
現代の日本で「伝統的なお茶は何か」と聞けば、多くの人は粉末の抹茶をお茶碗に入れて茶筅で点てる(たてる)「茶道」とお答えになるだろう。陶磁器も茶道具の器として発展したと広く信じられている。
では、もう一つの茶、「煎茶」と呼ばれている急須で淹れた(いれた)透きとおったお茶を日本人が飲み始めたのはいつ頃のことかご存知だろうか。
江戸時代のはじめ、京都の宇治にある萬福寺を開いた隠元(1592-1673)が日本に急須をもたらした人物であると言われている。江戸時代の中頃、京の南に位置する宇治で茶園を営んでいた永谷宗円(1681~1778)は煎茶用の茶葉の製法を開発した。
ちょうど同じころ、長崎で中国式の茶の淹れ方を学んだ禅僧の売茶翁(1675-1763)が京の各所で簡素な席を設けて茶をふるまった。

すると、京、大坂、そして西日本の港町の裕福な町人や知識人がこの急須を使って淹れる新しい茶に注目し始めたという。京では絵師の伊藤若冲(1716-1800)、池大雅(1723-1776)、俳人の与謝蕪村(1716-1784)らが売茶翁と親交があったことで知られている。このように煎茶を淹れる道具が一般の人々の間に普及したのは江戸時代の終わりの頃のようである。
当時の日本人にとっての海外といえば中国だった。国外への渡航は禁止されており決して行くことはできない憧れの地。そこから、絶えず新しい文化がもたらされ続けていた。
実際に中国人が居住していた長崎はもとより、歴代の住職の多くが中国からの渡来僧であった宇治の萬福寺は先進文化の発信地という役割も担っていた。海を渡ってもたらされてくる珍しい書籍や絵画・文房具などに触れ、江戸時代の知識人は彼の地に思いを馳せていたのである。
同じように煎茶用の道具も多くは長崎を通じて日本に輸入されていた。しかし、その人気は日に日に高まり輸入品だけでは足りなくなったらしい。やがて中国製品を模倣した日本製の急須や茶碗がつくられるようになる。

ここで活躍したのが清水寺の麓に位置する五条坂の陶工たち。例えば、代々続く京焼の名家、六兵衛家の初代清水六兵衛(1738~1799)は急須の腕前で名を上げたことが知られている。こうした京焼の陶工の役割は、煎茶の茶書『清風瑣言』を著したことで知られる上田秋成(1734-1809)の言葉にもみられる。
「古渡の茶瓶たまたま得るたらば、京師の名工に模さしめ、破壊の厄に備ふべし」
『清風瑣言 巻之下』

この一文を現代風に訳せば「外国産の古い急須を手に入れた場合は、万が一の場合に備えて京の陶工に模倣品を作らせるように」である。京都以外の産地でも煎茶道具を造ったところはあるが、その質・量ともに江戸後期の京焼に勝るところはない。
これは、お手本にする中国産の「本物」が京や大坂の裕福な町人や寺院に集まっていたこと。そして、大都市に近く最新の流行に敏感に対応できたことが原因だろう。
当初、京都では煎茶で使う茶碗や花瓶の素材として必要な磁器を焼くことはできなかった。そこで研究を重ねて、初めて磁器の焼成に成功したのが奥田潁川(1753~1811)であるという。その技術を弟子たちに受け継いだ彼の功績により、京焼の主力製品に磁器が加わることとなった。 江戸時代の後期に活躍した欽古堂亀祐(1765~1837)、青木木米(1767~1833)、仁阿弥道八(1783~1855)、尾形周平(1788~1839)、永楽保全(1795~1854)等の作品からは彼らが模範とした外国製の陶磁器に対する憧れや、その再現を目指す真摯な情熱を垣間見ることができる。

著者 : 前崎信也