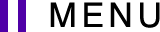「京焼」とは何を意味するのか?

フィラデルフィア万博で日本の陶磁史を代表する作品に選ばれた中には、樂家五代宗入の黒楽茶碗*、七代長入の赤楽・黒楽茶碗二碗*、十代旦入の赤楽・黒楽茶碗二碗* *が含まれていた。前回紹介した本阿弥光悦の黒楽茶碗も含めれば、少なくとも六碗の楽茶碗がそこにはあった。しかし、「京焼」の定義の仕方によっては、これら六碗の楽茶碗は京焼ではなくなることをご存じだろうか。
今回で第三回となる本連載、これまであえてこの京焼の定義問題について触れないで話を進めてきたが、ここで少しだけ触れておこうと思う。京都の陶芸家の方々に「京焼を研究しています」と自己紹介をさせていただくと、よく「前から気になっていたのですが、京焼とはどんなやきものを指す言葉ですか?」と聞かれる。一般の方から同じような質問をされて、何と答えるのが正しいのかわからず困っておられるのだそうだ。しかし、実はこれは、真面目に答えようとすると何時間もかかるような、一筋縄ではいかないややこしい問題なのである。なぜなら、時代によって「京焼」の範囲は変わり続けてきたからだ。
大手前大学の岡佳子先生が、この「京焼とは何なのか?」問題について、『近世京焼の研究』(思文閣出版、2011年)という本の中で解説されている。この本に時代ごとに「京焼」という言葉の意味するものがいかに変化してきたかについてや、先程述べたように「楽焼」を「京焼」に含めなくなった背景についても説明がある。これは実に面白い話なのだけれども、詳しく説明していると長くなり過ぎるので、「京焼」問題にご興味のある皆様には是非、岡先生の本を読んでいただきたい。
この連載で「京焼」と述べる際には、岡先生が使われている定義、つまり「近世以後に京都で焼かれたやきもの」に従っている。近世とは日本史では安土桃山時代から江戸時代にあたる。そして、京都というのは京都市街地とその周辺とされている。つまり、安土桃山時代以降に現在の京都市内とその周辺地域で作られた陶磁器が、本連載のいう「京焼」であるということにしたい。
粟田口 対 清水・五条坂
「京焼」という言葉が、現在のように使われるようになった背景について少しお話しよう。現在知られている中で、「きょうやき」という言葉が使われた最初は慶長十年(1605年)のこと。『宗湛日記』という書物の慶長十年六月十五日の条に「肩衝 京ヤキ」とあるのがそれだという。しかし、ここで登場する「京ヤキ」が、一体どのようなやきものを意味するのかという問題については、いまだ完全には解明されていない。つまり、この「肩衝 京ヤキ」という記載からわかる事は、何らかの京都に関係した肩衝茶入(肩の張った茶入)がこの頃に使われていたということだけなのである。
以後、野々村仁清、尾形乾山、奥田潁川、木米など、多くの有名陶工が現れた京都。おしゃれな江戸時代の人々を楽しませようと、スタイルを変化させ、またおのおのが競い続けてきた。つまり、「京焼」というような曖昧な言葉を使うよりも、それぞれの地域や窯、陶工の名前を使った方が便利だったことは想像に難くない。
その上、歴史的に見てみると江戸時代後期の粟田口と清水・五条坂の陶工はあまり仲が良くない。清水・五条坂の窯元が粟田焼の陶土を買い占めたり、粟田口の職人を雇って粟田焼のコピーをしていたために裁判になったり、というような記録もある。[1]そして、「粟田の陶家は五条坂に移らない。五条坂の陶工も粟田へは移らない。五条坂の職工は粟田には雇わない。粟田よりの門人は五条坂には受付けない。」[2]というような掟があったという。そういうわけで、江戸時代には、粟田口と清水・五条坂を、「京焼」というような言葉で一括りにするというのはまさにとんでもない話だったのである。
では、「京焼」の存在意義が生まれたのはいつ頃なのかというと、それはやはり明治時代のことである。なぜなら、廃藩置県をきっかけに、国内・国外の博覧会への出品は府県単位にかわった。陶磁器に限らずどのような分野でも、京都府が他の府県よりもいかに優れているかを競うという時代になったのである。こうして、他府県や外国という競争すべき「他者」を意識して初めて、京都としてひとつにまとまる必要性が生まれた。

二代真清水蔵六(図2)は昭和初期に幕末から明治期の京焼について多くの記録を遺した人物である。彼はこの変化について以下のように述べている。
「明治維新後に五条坂と粟田との紛議が解けたと云ふのは、貿易奨励の為に政府より外国博覧会へ日本より始めて人民に出品の製品を命ぜられ、旧幕時代には粟田は色絵金彩色は焼いても、五条坂は焼けないと云ふ様な禁止令は未開なることだが、幕政時代の事は次第に消滅をしたのであった。」[3]
とはいえ、京都の陶磁器を指す言葉として当時一般的であったのは、「山城京都焼」、「京窯」といった言葉だった。「京焼」という言葉が使われはじめたのが大正~昭和初期、一般的に使われるようになったのはさらに遅れて戦後のことである。
こういった背景を知ってあらためて「京焼」を考える。すると、それは一体何なのかという問題についての答えが見えてくる。それは、「京焼」は京都のやきものが他の産地や他の国の製品と闘う時にのみ使われるべき言葉であるということ。そして、その意味は簡単に述べれば「Ceramic wares made in Kyoto」ということでしかないということである。
京都は過去、常に京都の中で切磋琢磨し、種々の新しい陶磁器を生み出し続けてきた。その頃には「京焼」という地域でひとくくりにする言葉を使う必要などなかった。なぜなら、「粟田焼」「清水焼」の他にも、「仁清」「乾山」「楽」「木米」「六兵衛」「道八」「永楽」「真葛」など、それぞれの窯元が各々の名前だけで勝負をしていたからである。
「うちは京焼とは違う。京都だからといって安易に全部一緒くたにされては困る」というような意識が、江戸後期以降、日本の陶磁器業の中心であり続けた京都の陶磁器業の根幹にあった。私にはそう思えてならないのである。

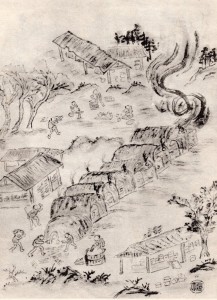
[1] 中ノ堂一信『京都窯芸史』淡交社、1984年、90-92頁
[2] 真清水蔵六『古今京窯泥中閑話』永澤金港堂、1935年、50頁
[3] 同上、67~68頁