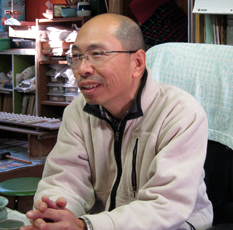 中国で初めて焼かれた釉陶(上薬がかかった焼き物)は、青磁であるとの説もある。横山さんは、主にその青磁の器を製作されていて、食器と茶道具の両方を手がけられる。
中国で初めて焼かれた釉陶(上薬がかかった焼き物)は、青磁であるとの説もある。横山さんは、主にその青磁の器を製作されていて、食器と茶道具の両方を手がけられる。
釉陶は、古くは中国が殷(紀元前1600年~紀元前1028年)の時代からあるそうで、灰を水に溶かして、すっぽりと器にかけ1200度から1300度の高温で焼き上げたものだが、灰の中に、自然に含まれる鉄分によって、器の表面が青緑色もしくは緑色に発色する。これが青磁の器の原型だ。
横山さんは、この青磁の釉薬を祖父の時代から伝えられた割合で、自家にて調合されている。
 その色合いは、単なる鉄分だけによる青緑色というものではなく、発色剤として微量のコバルトやクロムなども含まれた、青磁としては深みのある発色を呈する。
その色合いは、単なる鉄分だけによる青緑色というものではなく、発色剤として微量のコバルトやクロムなども含まれた、青磁としては深みのある発色を呈する。
横山さんの御祖父の時代からの割合で、そのまま同じように調合されているとのことだが、やはり、その時代と比べて、現在では原料の質の変化や、原料によっては、そのものが今では手に入らないなど、昔のものとは焼き上がりの色合いが微妙に違ってくることは否めない。
 横山さんは、「原料の質の変化で当時の青磁の色合いと違ってくることは、それはもう仕方がない事ですね。おじいさんの調合ノートを見ても、当時の呼び名で書いてある原料もあり、今となっては、これは何だ?と、思うような不明な原料もあります。」と、笑って言われる。
横山さんは、「原料の質の変化で当時の青磁の色合いと違ってくることは、それはもう仕方がない事ですね。おじいさんの調合ノートを見ても、当時の呼び名で書いてある原料もあり、今となっては、これは何だ?と、思うような不明な原料もあります。」と、笑って言われる。
横山さんの作品で、特に目を見張ったのは、器の側面全体に大胆に透かし彫りを施した作品で、その丁寧に彫られた模様から長い時間をかけて、じっくり作り上げられたことが伺える逸品である。「透かし彫りの作業は、まだ器が土から乾ききっていない、柔らかいうちに彫ってしまわないとできないのです。」と横山さんは言う。
 全面に透かし彫りを施す作業は、短時間で完結できないのは明らかだ。湿った布で器を覆い、乾ききらないように面倒を見ながら、彫りの作業を丁寧に進めるのである。この透かし彫りの作品は、中国の耀州窯で焼かれた青磁の透かし彫りの作品に通ずるものを感じる。
全面に透かし彫りを施す作業は、短時間で完結できないのは明らかだ。湿った布で器を覆い、乾ききらないように面倒を見ながら、彫りの作業を丁寧に進めるのである。この透かし彫りの作品は、中国の耀州窯で焼かれた青磁の透かし彫りの作品に通ずるものを感じる。
横山さんの作品の中には、青磁以外にも黄磁の作品もあり、こちらは中国の郊壇官窯で焼かれていた「米色青磁」に通ずる雰囲気を感じる。浮き彫りで草花模様を施された白磁の器も実に美しい。
 浮き彫りによって模様を施され、透明釉(白磁)や青磁の上薬をかけられたものは、その模様の輪郭に透明釉が溜まり、陰影が生まれる。この陰影の部分を陶磁器では影青(インチン)と呼ぶのだが、横山さんの作品はこの影青の美しさが清々しい。
浮き彫りによって模様を施され、透明釉(白磁)や青磁の上薬をかけられたものは、その模様の輪郭に透明釉が溜まり、陰影が生まれる。この陰影の部分を陶磁器では影青(インチン)と呼ぶのだが、横山さんの作品はこの影青の美しさが清々しい。
「私がやっているような、こういう仕事は、継いでいこうという若い人が、今はほとんどいません。面倒な作業ですからね。」横山さんは残念そうに言われるが、「簡単に量産できる作品ではありませんから、知り合いやお得意様など、個人的につながりのある方に直接お売りさせていただいています。」
横山さんの作品は、心を込めて作られたものが、横山さんご自身の手で直に、購入者に手渡される。正に、購入者にとって他にない逸品なのである。これからも、長く作品造りに励まれるよう願いたい。

横山武司
京焼・清水焼は永く王城の地、京都に江戸時代初期、仁清・乾山などの名工が輩出して、
その祖を築き、その永い伝統が現在に続いています。私は、この清水焼のなかで、
二代目瑞祥の薫陶を受け青磁、黄磁など、もっぱら色釉の磁器に独特の境地をだしています。
| 1956年 京都市生まれ |
| 1974年 京都市立日吉ケ丘高校卒 |
| 1979年 家業に従事 |
| 2006年 伝統工芸士に認定される |
| 京焼・清水焼商工会議所会頭賞 |
| 京都青窯会作陶展京都新聞社賞 |
| 京都商工会議所会頭賞 |
京焼・清水焼 瑞祥窯 伝統工芸士 横山武司
〒605-0976 京都市東山区泉涌寺東林町35
TEL:075-561-6263


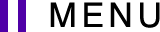
















 そういう性質を持つ陶磁器の色絵の具で、これほどの色のパターンを自ら作り出され、それを駆使して色絵を施されている入江さんの仕事に、脱帽させられる思いだ。色絵の具は、窯の温度の上げ下げや、窯の中のどの位置において焼いたかによっても、色の出方は違ってくることがある。また前回と同じ色に上がってくるかは、いつも心配だと入江さんは話されるが、長年、色絵の焼き物を焼いてこられて、今現在でも、なかなか満足のいく仕事にならないとも話される入江さんの言葉に、より完璧なものを追求したいという職人魂のようなものを感じる。
そういう性質を持つ陶磁器の色絵の具で、これほどの色のパターンを自ら作り出され、それを駆使して色絵を施されている入江さんの仕事に、脱帽させられる思いだ。色絵の具は、窯の温度の上げ下げや、窯の中のどの位置において焼いたかによっても、色の出方は違ってくることがある。また前回と同じ色に上がってくるかは、いつも心配だと入江さんは話されるが、長年、色絵の焼き物を焼いてこられて、今現在でも、なかなか満足のいく仕事にならないとも話される入江さんの言葉に、より完璧なものを追求したいという職人魂のようなものを感じる。 器に描かれるデザインも、もちろん入江さんのオリジナルのものだが、その幾何学模様の正確さや、細かさにも驚かされる。手描きで、ここまで描けるのかと思えるほどの、正確で美しい模様が器に施され、見ているだけでも、その世界観にすっと、入り込んでいく感じがする。正確で細かな模様であり、これを手描きするのは、いかにも大変であろうと思うのだが、入江さんは「こういう模様の方が、私は楽なんです。」と話される。おそらく、入江さんご自身がお好きな模様なのだろう。そして、その模様の絵付けをされているとき、楽しく作業をされている姿が想像される。その楽しく絵付けをされた雰囲気までもが、器から伝わってくる。これこそが、入江さんの色絵の器の魅力なのかもしれない。
器に描かれるデザインも、もちろん入江さんのオリジナルのものだが、その幾何学模様の正確さや、細かさにも驚かされる。手描きで、ここまで描けるのかと思えるほどの、正確で美しい模様が器に施され、見ているだけでも、その世界観にすっと、入り込んでいく感じがする。正確で細かな模様であり、これを手描きするのは、いかにも大変であろうと思うのだが、入江さんは「こういう模様の方が、私は楽なんです。」と話される。おそらく、入江さんご自身がお好きな模様なのだろう。そして、その模様の絵付けをされているとき、楽しく作業をされている姿が想像される。その楽しく絵付けをされた雰囲気までもが、器から伝わってくる。これこそが、入江さんの色絵の器の魅力なのかもしれない。 色絵を焼く窯にも、入江さんはこだわっておられる。普通、色絵は「錦窯(きんがま)」と呼ばれる丸形の電気窯で焼くのだが、入江さんの窯は本焼きなどでも使われる四角い電気窯を使っておられる。この四角の電気窯の方が調子が良く、色が綺麗に上がるのだとか。格調高い作品に仕上げられることに余念がない。
色絵を焼く窯にも、入江さんはこだわっておられる。普通、色絵は「錦窯(きんがま)」と呼ばれる丸形の電気窯で焼くのだが、入江さんの窯は本焼きなどでも使われる四角い電気窯を使っておられる。この四角の電気窯の方が調子が良く、色が綺麗に上がるのだとか。格調高い作品に仕上げられることに余念がない。

 備前焼の大家で陶芸の修業をされた出口鯉太郎さんが作られる作品は土味を生かした素朴な風合いのものが多い。備前での修業時代は、土作りから教わったそうで、今でも作品はまず、土作りから始めることを大切にされている。山から掘り出された原土を陶芸に使える土にするまで時間を掛けて行われる。
備前焼の大家で陶芸の修業をされた出口鯉太郎さんが作られる作品は土味を生かした素朴な風合いのものが多い。備前での修業時代は、土作りから教わったそうで、今でも作品はまず、土作りから始めることを大切にされている。山から掘り出された原土を陶芸に使える土にするまで時間を掛けて行われる。 出口さんが現在、作陶を続けられるのは亀岡市内。工房は市街地の中矢田というところにあるが、宮前町神崎三泥という周囲を山に囲まれた所に穴窯を持っておられて、その窯で作品を焼かれている。松割り木で熾される炎で焼かれる出口さんの作品は、その炎が当たることで作り出される色合いや光沢が自然で素朴な味わいの作品だ。正に炎芸術である。 出口さんに、作品を作る上でのコンセプトは何かと尋ねると「あるがまま」という答えが返ってきた。我が意図するところ以上に炎が作り出す焼き物であり、無意味な奇をてらわないあるがままの作品なのである。
出口さんが現在、作陶を続けられるのは亀岡市内。工房は市街地の中矢田というところにあるが、宮前町神崎三泥という周囲を山に囲まれた所に穴窯を持っておられて、その窯で作品を焼かれている。松割り木で熾される炎で焼かれる出口さんの作品は、その炎が当たることで作り出される色合いや光沢が自然で素朴な味わいの作品だ。正に炎芸術である。 出口さんに、作品を作る上でのコンセプトは何かと尋ねると「あるがまま」という答えが返ってきた。我が意図するところ以上に炎が作り出す焼き物であり、無意味な奇をてらわないあるがままの作品なのである。 地面に直接煉瓦を積み上げて作られる穴窯は、雨が降れば地中に染み込んだ水分で湿気を持つ。年に数回の窯焚きの間には雨が降る日も当然あるので、窯を焚くためには最初、窯に含まれる湿気を抜くことから始めなければならない。その湿気を抜くための”焙り(あぶり)”は雑木を燃やして行う。
地面に直接煉瓦を積み上げて作られる穴窯は、雨が降れば地中に染み込んだ水分で湿気を持つ。年に数回の窯焚きの間には雨が降る日も当然あるので、窯を焚くためには最初、窯に含まれる湿気を抜くことから始めなければならない。その湿気を抜くための”焙り(あぶり)”は雑木を燃やして行う。 出口さんに生い立ちのことを訊いてみた。出口さんの祖母は石黒宗麿に陶芸を教わった女流陶芸家の先駆けであったそうで、出口さんの窯名である東白窯は石黒宗麿が名付け親だそうだ。
出口さんに生い立ちのことを訊いてみた。出口さんの祖母は石黒宗麿に陶芸を教わった女流陶芸家の先駆けであったそうで、出口さんの窯名である東白窯は石黒宗麿が名付け親だそうだ。 出口さんの窯場の敷地内には、「ウリズン」という名称の施設が隣接している。この「ウリズン」とは、あるNPO団体が建てたもので、宿泊や会合に誰でもが利用できる施設になっている。長閑な山中にあるこの施設は周りの森の景色にすんなりとけ込むような木造の建屋で、休暇をこの施設で過ごしたいと思えるようなところ。
出口さんの窯場の敷地内には、「ウリズン」という名称の施設が隣接している。この「ウリズン」とは、あるNPO団体が建てたもので、宿泊や会合に誰でもが利用できる施設になっている。長閑な山中にあるこの施設は周りの森の景色にすんなりとけ込むような木造の建屋で、休暇をこの施設で過ごしたいと思えるようなところ。


 住宅街の中にあるバス停から、たった15分ほども歩いただけで、周りは長閑な山村のような風景にガラリと変わった。田中宣夫さんの工房は都会の喧噪から離れるように、その地に建っている。
住宅街の中にあるバス停から、たった15分ほども歩いただけで、周りは長閑な山村のような風景にガラリと変わった。田中宣夫さんの工房は都会の喧噪から離れるように、その地に建っている。 元々、田中さんは田中姓ではなかった。結婚される際、奥様の籍に入る形を取られて田中姓になられたのだが、そのことに迷いはなかったそうだ。現在は、ご夫婦で仲良く作陶を続ける日々を過ごされている。ご主人の田中さんが主に轆轤で器を作り、それに奥様が絵付けをする共同作業で作品が作られていく。
元々、田中さんは田中姓ではなかった。結婚される際、奥様の籍に入る形を取られて田中姓になられたのだが、そのことに迷いはなかったそうだ。現在は、ご夫婦で仲良く作陶を続ける日々を過ごされている。ご主人の田中さんが主に轆轤で器を作り、それに奥様が絵付けをする共同作業で作品が作られていく。 茶道具は季節感を盛り込んだデザインを要求されることが多い。春は桜、夏は紫陽花、秋は紅葉、冬は椿や牡丹といった、その季節を表す草花の図案を施すことが多いが、去年の桜と今年の桜では、テーマが同じ桜でも少しずつ違った図案を考案して絵を描かなければならない。毎年、違った桜の図案、紅葉の図案を幾パターンも考え続けていかなければならない厳しい面もある。
茶道具は季節感を盛り込んだデザインを要求されることが多い。春は桜、夏は紫陽花、秋は紅葉、冬は椿や牡丹といった、その季節を表す草花の図案を施すことが多いが、去年の桜と今年の桜では、テーマが同じ桜でも少しずつ違った図案を考案して絵を描かなければならない。毎年、違った桜の図案、紅葉の図案を幾パターンも考え続けていかなければならない厳しい面もある。 田中さんは、これら次々と産み出される作品を発表する場を意欲的に求められている。昨年は、京都市内の町屋で展覧会を開催されたり、全国各地で開催される陶器のイベントにも積極的に出展されている。実際に作品を使って頂く方との直接の関わりを大切に考えておられるのだ。ご自身の作品を購入して下さる方と直に接してのやりとりを、心から楽しいと感じておられる。
田中さんは、これら次々と産み出される作品を発表する場を意欲的に求められている。昨年は、京都市内の町屋で展覧会を開催されたり、全国各地で開催される陶器のイベントにも積極的に出展されている。実際に作品を使って頂く方との直接の関わりを大切に考えておられるのだ。ご自身の作品を購入して下さる方と直に接してのやりとりを、心から楽しいと感じておられる。

 京都府綴喜郡井手町で作陶される北川宏幸さんは、とても穏やかなお人柄で、優しさがにじみ出るような方だ。北川さんは、この地で雅号を「陶房 弥三郎」と銘打ち、作陶を続けられている。さて、弥三郎の名前の由来はなにか?ふと、疑問に思ったので北川さんに訊いてみたところ、北川さんの生家は代々この井手町に続く家柄で、その家の屋号なのだそうだ。元々は農家であったが、北川さんのお爺さんは、竹細工の名工でもあったらしい。やはり、その物作りの血を受け継がれたのだろう。北川さんが、陶芸の道を志すことを決められたのは高校生の時。当時、流行であった民芸ブームの中、加藤唐九郎や荒川豊蔵といった花形の陶芸作家の作品を見てあこがれ、心に決められたそうだ。そして、京都造形芸術学院陶芸科に進み、在学中に天目釉の名匠である陶芸作家、木村盛康氏に弟子入りされた。
京都府綴喜郡井手町で作陶される北川宏幸さんは、とても穏やかなお人柄で、優しさがにじみ出るような方だ。北川さんは、この地で雅号を「陶房 弥三郎」と銘打ち、作陶を続けられている。さて、弥三郎の名前の由来はなにか?ふと、疑問に思ったので北川さんに訊いてみたところ、北川さんの生家は代々この井手町に続く家柄で、その家の屋号なのだそうだ。元々は農家であったが、北川さんのお爺さんは、竹細工の名工でもあったらしい。やはり、その物作りの血を受け継がれたのだろう。北川さんが、陶芸の道を志すことを決められたのは高校生の時。当時、流行であった民芸ブームの中、加藤唐九郎や荒川豊蔵といった花形の陶芸作家の作品を見てあこがれ、心に決められたそうだ。そして、京都造形芸術学院陶芸科に進み、在学中に天目釉の名匠である陶芸作家、木村盛康氏に弟子入りされた。  そんな、北川さんの作品は天目釉と飛び鉋、櫛目を組み合わせた作品で、土が持つ可塑性と釉薬の窯変性を生かしたものになっている。特に釉薬は油滴天目釉の表面に析出する金属の微細な結晶により、微かな金属光沢を放つ。北川さんは、これを耀変鉄釉と呼んでいる。飛び鉋と櫛目で模様付けされる部分は焼〆象嵌と呼び、その二つを対比させることで、金属的でシャープな感覚の作品に仕上げておられるそうだ。この耀変鉄釉と焼〆象嵌を組み合わせた作品は「焼〆鉄黒様」と名付けておられる。 北川さんの作品は、この「焼〆鉄黒様」以外にも素朴な土ものの柔らかさが表現された作品も作られている。取材の折、作業風景を撮らせて欲しいとお願いしたところ、快く黄瀬戸の抹茶碗をろくろ挽きして下さったのだが、この時に驚いた。突然、茶碗を挽く北川さんの手がブルブルと大きく震えだしたのだ。
そんな、北川さんの作品は天目釉と飛び鉋、櫛目を組み合わせた作品で、土が持つ可塑性と釉薬の窯変性を生かしたものになっている。特に釉薬は油滴天目釉の表面に析出する金属の微細な結晶により、微かな金属光沢を放つ。北川さんは、これを耀変鉄釉と呼んでいる。飛び鉋と櫛目で模様付けされる部分は焼〆象嵌と呼び、その二つを対比させることで、金属的でシャープな感覚の作品に仕上げておられるそうだ。この耀変鉄釉と焼〆象嵌を組み合わせた作品は「焼〆鉄黒様」と名付けておられる。 北川さんの作品は、この「焼〆鉄黒様」以外にも素朴な土ものの柔らかさが表現された作品も作られている。取材の折、作業風景を撮らせて欲しいとお願いしたところ、快く黄瀬戸の抹茶碗をろくろ挽きして下さったのだが、この時に驚いた。突然、茶碗を挽く北川さんの手がブルブルと大きく震えだしたのだ。  「五十歳を過ぎてから手が震えるようになってねぇ・・・、ガハハ」と北川さんは笑っておられたが、いや、そうではない。茶碗の側面に変化を付けて味を出すため、意図的に手を震わせて起伏を付けておられたのだ。筆者もろくろを回して器を作るし、今までに何人もの同業のろくろ師の作業を見てきたが、北川さんのような技は見たことがない。普通なら熟練の職人でも、ろくろで回転する土に対して触れている手を、あのように震わせたら当然の如く、器はグチャグチャになって潰れてしまう。それを、いとも簡単にこなしてしまう北川さんの技は、容易には真似のできない面白い技だ。
「五十歳を過ぎてから手が震えるようになってねぇ・・・、ガハハ」と北川さんは笑っておられたが、いや、そうではない。茶碗の側面に変化を付けて味を出すため、意図的に手を震わせて起伏を付けておられたのだ。筆者もろくろを回して器を作るし、今までに何人もの同業のろくろ師の作業を見てきたが、北川さんのような技は見たことがない。普通なら熟練の職人でも、ろくろで回転する土に対して触れている手を、あのように震わせたら当然の如く、器はグチャグチャになって潰れてしまう。それを、いとも簡単にこなしてしまう北川さんの技は、容易には真似のできない面白い技だ。  北川さんは個展だけでなく、日本各地で行われている焼き物市にも積極的に出展される。直に、器を買いに来られる人と触れ合って作品を提供することに意気を感じておられるのだ。第一回目として今年から開催される「やきものフェアinみやぎ」にも出展されるそうだ。今まで出展したことがない焼き物市にも、あえて赴かれるのは、東日本大震災の被災地である宮城で初めて開催される焼き物市だからこそ、応援する意味でも参加したいのだとのこと。やはり、ここでも、心優しき陶芸家の北川さんなのである。
北川さんは個展だけでなく、日本各地で行われている焼き物市にも積極的に出展される。直に、器を買いに来られる人と触れ合って作品を提供することに意気を感じておられるのだ。第一回目として今年から開催される「やきものフェアinみやぎ」にも出展されるそうだ。今まで出展したことがない焼き物市にも、あえて赴かれるのは、東日本大震災の被災地である宮城で初めて開催される焼き物市だからこそ、応援する意味でも参加したいのだとのこと。やはり、ここでも、心優しき陶芸家の北川さんなのである。 
 京都府と奈良県の県境に接する自然豊かな木津川市鹿背山で作陶される福田翔さんの工房は、あらゆる題材をモチーフにした絵が描かれた焼き物であふれている。福田さんは、ご自身のことを“絵付け職人”と自ら称されるが、与えられた既存の模様を施すだけの絵付け職人の域に留まらない、オリジナリティーに富んだ絵付けをされた焼き物がずらりと並ぶ。
京都府と奈良県の県境に接する自然豊かな木津川市鹿背山で作陶される福田翔さんの工房は、あらゆる題材をモチーフにした絵が描かれた焼き物であふれている。福田さんは、ご自身のことを“絵付け職人”と自ら称されるが、与えられた既存の模様を施すだけの絵付け職人の域に留まらない、オリジナリティーに富んだ絵付けをされた焼き物がずらりと並ぶ。 福田さんに、多大なる影響を与えたその人物とは、村田幸之介という絵付け師で、独自の水墨画法を持ち、たたみ一畳ほどもある大きな陶板に、瞬く間に風景画を描いてしまうほどの名人であったらしい。福田さんは、この村田幸之介氏から水墨画法を吸収し、それを自らのものとして焼き物に施す技法を身につける。独立する際には、単色の濃淡だけで表現する南画風の絵付けに加え、色絵も取り入れたオリジナルの画風を完成させた。福田さんは、この画法をご自身で「墨彩画」と称されている。
福田さんに、多大なる影響を与えたその人物とは、村田幸之介という絵付け師で、独自の水墨画法を持ち、たたみ一畳ほどもある大きな陶板に、瞬く間に風景画を描いてしまうほどの名人であったらしい。福田さんは、この村田幸之介氏から水墨画法を吸収し、それを自らのものとして焼き物に施す技法を身につける。独立する際には、単色の濃淡だけで表現する南画風の絵付けに加え、色絵も取り入れたオリジナルの画風を完成させた。福田さんは、この画法をご自身で「墨彩画」と称されている。 福田さんの絵の題材となるものは、ありとあらゆるもの。工房のすぐ脇に咲く花や野草、近くの木に停まる小鳥、町に出たときにスケッチした大阪中之島の風景、勇壮な龍、それこそ福田さんの絵の題材は事欠かない。そして、焼き物の素地は福田さんにとってカンバスなのである。
福田さんの絵の題材となるものは、ありとあらゆるもの。工房のすぐ脇に咲く花や野草、近くの木に停まる小鳥、町に出たときにスケッチした大阪中之島の風景、勇壮な龍、それこそ福田さんの絵の題材は事欠かない。そして、焼き物の素地は福田さんにとってカンバスなのである。
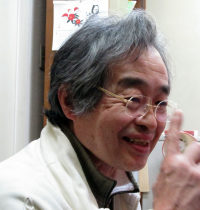 伝統工芸士である藤田瑞古さんは、広島県の生まれ。陶器とは何ら関係のない家庭に生まれ、高校卒業時も進路は金融機関に就職が決まっていた。しかし、祖母から「これからの時代は手に職を付けた方がいい。」と言われ、親戚である京都では有数の規模を誇る大きな製陶所で一転、職人を目指すこととなった。
伝統工芸士である藤田瑞古さんは、広島県の生まれ。陶器とは何ら関係のない家庭に生まれ、高校卒業時も進路は金融機関に就職が決まっていた。しかし、祖母から「これからの時代は手に職を付けた方がいい。」と言われ、親戚である京都では有数の規模を誇る大きな製陶所で一転、職人を目指すこととなった。 そんな藤田さんが仕事をされる工房は、コンパクトに作られた工房だが、非常に効率的に考えられた造りになっている。職人の間でつぶやかれる言葉に「仕事するより段取りせい。」という言葉がある。これは、手作業にかかる前に頭の中で、仕事の順序を事前によく考えてから作業にかかりなさいという意味で、職人の仕事とは、効率良く作業を進めてこそ価値があるという戒めである。藤田さんもコンパクトで効率的な自身の工房で「段取り8分、仕事2分」ということを常に念頭に置いて仕事をされているそうだ。
そんな藤田さんが仕事をされる工房は、コンパクトに作られた工房だが、非常に効率的に考えられた造りになっている。職人の間でつぶやかれる言葉に「仕事するより段取りせい。」という言葉がある。これは、手作業にかかる前に頭の中で、仕事の順序を事前によく考えてから作業にかかりなさいという意味で、職人の仕事とは、効率良く作業を進めてこそ価値があるという戒めである。藤田さんもコンパクトで効率的な自身の工房で「段取り8分、仕事2分」ということを常に念頭に置いて仕事をされているそうだ。 藤田さんが作られる焼き物は磁器を専門とされる。発注者の希望に添うように形やデザインに気を遣い作られている。「私の技術は問屋さんや小売店さんに鍛えられた技術」と藤田さんが語られるように、藤田さんの作品はとても繊細で美しい。限界まで薄く作られた磁体に華麗な染付や上絵付けが施されている割烹食器がメイン。
藤田さんが作られる焼き物は磁器を専門とされる。発注者の希望に添うように形やデザインに気を遣い作られている。「私の技術は問屋さんや小売店さんに鍛えられた技術」と藤田さんが語られるように、藤田さんの作品はとても繊細で美しい。限界まで薄く作られた磁体に華麗な染付や上絵付けが施されている割烹食器がメイン。 「今までの染め付けや上絵付けだけでなく、漆塗りなどの伝統技法も加え、これからの焼き物を作るということを考えてもいいのではないか。」と、藤田さんは先の展望を語られる。藤田さんの意欲的な仕事は、これからも続くのである。
「今までの染め付けや上絵付けだけでなく、漆塗りなどの伝統技法も加え、これからの焼き物を作るということを考えてもいいのではないか。」と、藤田さんは先の展望を語られる。藤田さんの意欲的な仕事は、これからも続くのである。
 「若い世代の人に陶器はお洒落と感じてほしい。」と話すのは、昭阿弥窯の高野洋臣さん。精巧で綿密な絵を施す茶器から、割烹、一般食器までを製作する昭阿弥窯の次代を担う若き職人である。 高野さんをあえて職人と呼ぶには訳がある。磁器を専門に製作する窯元では、ロクロの技術が如何に精確であるかを求められるからだ。ご本人も磁器が得意、ロクロ挽きを追求し、こだわりを持って製作していきたいと、自らの方針を話す。
「若い世代の人に陶器はお洒落と感じてほしい。」と話すのは、昭阿弥窯の高野洋臣さん。精巧で綿密な絵を施す茶器から、割烹、一般食器までを製作する昭阿弥窯の次代を担う若き職人である。 高野さんをあえて職人と呼ぶには訳がある。磁器を専門に製作する窯元では、ロクロの技術が如何に精確であるかを求められるからだ。ご本人も磁器が得意、ロクロ挽きを追求し、こだわりを持って製作していきたいと、自らの方針を話す。 「手仕事は基礎が大切、昔に比べて職人仕事が少しずつ廃れてきているのではないかとの危機感を持っています。」とは高野さんの弁。 確かに、しっかりとした基礎の上に芸術的、工芸的な仕事は成り立っている。かのピカソも若い頃に描いた精巧なデッサンを数多く残している。後の絵からは連想もできないような絵画の基礎を基に対象物を忠実に描いたものだ。精巧な茶器や食器を製作する昭阿弥窯の仕事以外にも、高野さんオリジナルの作品も意欲的に製作している。グループ展も定期的に開催し、高野さん自身のオリジナリティーを盛り込んだ作品を発表しているそうだ。
「手仕事は基礎が大切、昔に比べて職人仕事が少しずつ廃れてきているのではないかとの危機感を持っています。」とは高野さんの弁。 確かに、しっかりとした基礎の上に芸術的、工芸的な仕事は成り立っている。かのピカソも若い頃に描いた精巧なデッサンを数多く残している。後の絵からは連想もできないような絵画の基礎を基に対象物を忠実に描いたものだ。精巧な茶器や食器を製作する昭阿弥窯の仕事以外にも、高野さんオリジナルの作品も意欲的に製作している。グループ展も定期的に開催し、高野さん自身のオリジナリティーを盛り込んだ作品を発表しているそうだ。
