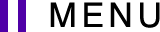藤信知子さんの作品は面白い。ユーモアと原始的な力に満ちたシャーマニズムのようなものを感じるのだ。
なぜ、あのような造形が生まれるのか不思議に思っていたら、本人から、祖父の死をきっかけに
非現実的な世界観、空想や妄想の世界といったものに関する作品を作りたいとの思いがあると聞いた。
そして作品を制作する中で、桃太郎など、昔の人達が空想した物語が今なお、語り継がれている事のすごさを感じているとのこと。
昔話の登場人物たちは藤信さんのこころのフィルターを通して、生き生きと動き出し、命がけでいたずらをして回る・・・
そんな気がする不思議な造形だ。
藤信さんは普段から「固定観念に縛られず、奇抜さ・面白さといったユーモアを大切にした楽しい作品」の制作を心がけているそうだが、
その作品は本当に自由で、楽しい。 藤信知子さんにしか作れない、不思議な世界を、ぜひ、お楽しみいただきたい。
<陶歴>
1988 大阪に生まれる
2010 京都精華大学芸術学部 素材表現学科陶芸専攻卒業
個展「さらば 愛しき日々 もう戻れぬ」ギャラリーアンテナ/京都
2011 トーキョーワンダーウォール公募 立体・インスタレーション部門 入選/東京都現代美術館
2012 京都精華大学 大学院芸術研究科 博士前期課程陶芸専攻修了
個展「花への挑戦状」 ギャラリー恵風/京都 京都美術・工芸ビエンナーレ2012 入選/京都文化博物館/京都
他、グループ展 多数

石清水八幡宮を仰ぐ山の脇道を進むと、その山すそに工房はあります。
都会の喧騒を隔てた静寂の中、うつわ作家として毎日ろくろと向き合っておられます。
窯から焼きあがった器は、それが何年も前からそこにあったような雰囲気をかもし出し、設えに溶け込むのです。
荒賀さんのうつわは、ろくろで土と会話をしているように、のびやかで、命をはらんだようにふっくらと愛おしい形をしています。
柔らかい光をまとったような粉引きを中心に、温かい肌合いの焼しめ、黒釉も素敵です。
前田さんのうつわは、レースのように細やかな模様が女性らしい、落ち着いた華やかさをたたえています。
どれも使う人の心地よさを一番に思って作られたうつわです。
人々のくらしのために作られたおふたりのうつわを、ぜひお手に取ってご覧ください。

100年ほど前に世界を魅了した京薩摩という京焼がありました。
虫眼鏡を使わないと細部まで見えないような超絶技巧を凝らしたその作風は、
世界中をあっと驚かせたのですが、永く絶えておりました。
それを現代に復興させたのが空女先生で、先生の作られる作品はその華麗さと細密さ、
そして今を生きる陶芸家としてのセンスで高い評価を得ておられます。
先生には素晴らしい作品を制作される作家としての顔と、
その技術を陶の道を歩む若い作家たちに惜しみなく伝授される、優れた指導者としての二つの顔があります。
今回はその両方をご紹介できる展覧会として開催させていただきます。
先生を慕う若き作家たちが日本中から集まり、それぞれの技を駆使した作品を披露してくれるのです。
「みんな違ってみんな良い…。」
と先生はおっしゃっておられました。
どんな煌めきが集まるのか…ぜひ、会場でご覧になっていただきたいと思います。
空女(小野多美枝)
<若手の出品作家9名>
見谷若葉、野上美映子、真砂皓志、竹内瑠璃、新川砂山、林大地、齋藤有希子、藤本友、高橋亜希

不思議な生命感のある造形・・・太田夏紀の作品は、表情豊かな動物たちが、それぞれ主張し合って世界を形成している。
どれもかわいいだけでない、シニカルな言葉を持って動き出すようだ。
カメレオン、カエル、スズメ、ランチュウ・・・今までの作品は実在の生物が太田風にアレンジされた
「松ぼっくりの雀」だったり、「歌うような鶏」や「神のようなナマケモノ」だった。
ところが今回の展覧会ではそこから一歩進んだ、見たことのない不思議な生物たちが登場する。
生物の奥底に潜んでいる、命の不可思議が、太田の手を通って地上に現れたような造形である。
かわいく、不気味で、得体のしれない新しい生き物たち。彼らはなにを想い、どこへ進んでいくのだろうか。
ますます太田の作品から目が離せない。
京都陶磁器会館2階ギャラリーが、太田夏紀の世界となる2週間・・・。是非、あなたの目で、不思議な命の世界をご覧ください。
太田夏紀(おおた なつき)
1993年 大阪府生まれ
2016年 京都精華大学 芸術学部素材表現学科 陶芸コース 卒業
2016年 京都精華大学 大学院 芸術研究科 陶芸専攻 入学
2015 「京都同時代学生陶芸展」元・立誠小学校/京都
2015年「わん・碗・ONE展」京都陶磁器会館/京都
2016年「合同個展」The Terminal KYOTO/京都
2016年「精華-ESSENCE-」BAMIgallery/京都
2016年「手のひらアート 動物園」岡山天満屋 COMBINEoffice/岡山
2016年「STEP/STROKE」ギャラリー恵風/京都
2016年「陶芸tomorrow 6芸大 若手の饗宴」ギャラリーマロニエ/京都
2016年「太田夏紀 個展 『息物』」BAMIgallery/京都
2016年「2017年 干支『酉達の集い』」あべのハルカス近鉄本店/大阪
2016年「-コンポラサーカス-京都若手現代美術作家展vol.2」京阪百貨店 守口店/大阪
受賞歴
2014年「わん・碗・ONE展」10位入賞 /京都陶磁器会館
2015年「京都花鳥館賞」優秀賞 /京都花鳥館

陳韋竹さんは動物や日本の玩具が好きで、強く影響を受けました。
そんな彼女の作品からは、おもちゃのような可愛らしさと、生き生きとした感情があふれ出てきます。
陳さんの作品は彼女自身の心の中に存在する空想の生き物ですが、
それらはまるで実際に存在するかのようで…幼いころに遊んだ記憶を思い出して欲しい…と観ている人へ語りかけます。
作品はすべて日本滞在中に制作されたもので「日本で彼女が感じたこと」が表現されています。
日本の土で焼き上げられた陳さんの動物たち。日本で陳さんが感じたことを、作品を通して感じていただければと思います。
<陳韋竹 略歴>
1987 台湾に生まれる
2013 アジア現代陶芸展 金沢21世紀美術館 愛知県陶磁美術館
2014 臺澳陶藝交流展 文化歴程 国立台湾芸術大学 澳門大学 台湾 香港
2015 国立台湾芸術大学 工芸設計学系研究所 陶芸科 卒業
信楽陶芸の森アートレジデンス滞在制作
虚疑動物的奇幻世界 桃園展演中心 台湾
アジア現代陶芸展 杭州 中國美術學院美術館 中國
第2回新北市陶藝奬「陶藝創新奬―創作組」入選
第7回台湾金陶奬「社會組」 審査特別奬‐作品典蔵
2016 夢の中の動物 藤喜陶苑 信楽
「よいの形」展 ギャラリーヴォイス 多治見
台湾国際陶藝雙年展 入選

マグカップは取手が犬の形をしていたり、お星さまやお花の形の重ね鉢だったり…
小野あやさんの作品はくらしをそっと見守ってくれるような優しさにあふれています。
テーブルに置いたら、素敵な誰かとの会話が始まりそうな、ありふれた日常をそっと支えて、楽しくしてくれる器です。
あなたのお気に入りを見つけに来てください。
1981年京都生まれ
2002年京都嵯峨芸術大学短期大学部陶芸コース卒業
2006年京都府立陶工高等技術専門校成形科修了
京都清水焼窯元嘉豊陶苑にて四年間就業
2011年京都市産業技術研究所技術者研修陶磁器コース修了
2012年京都市産業技術研究所技術者研修陶磁器応用コース修了
2013年京都市下京区にて開窯

京都青窯会協同組合は昭和43年発足の、皇室の御寺「泉涌寺」の麓に集う窯元で構成された組合です。
この泉涌寺の近辺は、「焼きもの」とは古くから縁があり、太閤秀吉が大仏殿造営にあたり、この地に瓦窯を築かせたのが始まりで、多くの瓦窯が存在していました。
その後、五条坂から移り住んだ先人達が登り窯を築いて、この地に開窯したのが大正3年。一番多い時で14基もの登り窯が煙を上げていた、京焼の産地です。
今も組合の拠点である「青窯会会館」を中心に、たくさんの窯元が制作に励んでいます。ここでは作品の展示はもちろんのこと、陶芸体験、工房見学など、幅広く京焼を味わう時間をお過ごしいただけます。
今回で49回目となる青窯会展では、テーマを「茶器」として、組合所属の窯元が腕によりをかけて日頃の成果を競います。
煎茶器、抹茶盌などの伝統の器から、ティータイムを彩る素敵な日常の器まで、生活の中で楽しんで使っていただける京焼が展示即売されます。 是非、ご高覧いただき、器の持つ「手作りのやさしい温もり」を感じてください。

山内 駿 陶展 –銀刻–
「銀刻彩」とは、山内駿氏が編み出した技法で、黒い陶器の上に銀を焼き付けた後、機械で銀を削り装飾するというものです。
美術館に展示されていた金属器の、年月を経て風化した表面の雰囲気に心動かされ、陶器でもこんな表現が出来ないかと模索した結果、辿り着いた技法がこれでした。
「機械を使い装飾する事は今の時代にしか出来ない表現であり、銀を削り陶の表面を出し陶器と金属を融合させる事は、
陶器だからこそ出せる金属の新たな表情」と言う、山内氏。 本来なら何百年も時が経ち風化していく表面を、機械の削りにより風化を刻んでいく、
時を刻むようなイメージで作品の表面を削っているそうです。
スタイリッシュでシャープな作品ですが、その中に込められた優しさが、見る人の心をひきつけます。
銀の冷たさの中に宿る手技の温もりや山内氏独特のユニークな形・・・これからが楽しみな若手作家です。
是非、ご高覧ください。
<陶歴>
1984年 京都で生まれ、宮城で育つ
2006年 京都伝統工芸専門学校 専攻科 卒業
猪飼祐一氏に師事
2009年 京都・東山にて独立
<展覧会>
2010年 ARTZONE(京都)
2011年 藤崎(仙台)[2013、15年]
2013年 米子髙島屋(鳥取)[2016年]
2015年 アートサロンくら(京都)
2016年 晩翠画廊(仙台)
ICFF出展(ニューヨーク)
ギャラリーみちかけ(京都)
<公募展>
2008年 日本伝統工芸近畿展 入選[09〜12、14〜16年]
2012年 京都府美術工芸新鋭展-2012京都美術・工芸ビエンナーレ- 招待出品
河北工芸展 秋田県知事賞 受賞
2014年 河北工芸展 入選
2016年 日本伝統工芸展 入選

京陶人形は京都で作られている素焼人形です。素焼人形は、粘土で形をこしらえ、乾燥させ、850℃くらいの低火度で焼成し、
顔料で彩色して仕上げたもので、全体が土という素材でありながら、やわらかなぬくもりを感じさせる深い味わいがあります。
人は太古の昔から、木や石や土など身近な材料で自分たちの似姿を作ってきました。
古墳時代には土で見事な土偶や埴輪を生み出し、やがて、型を使って多量に作られる時代になると、
安価で気取りのない庶民の愛玩用の人形として人々に親しまれてきました。京陶人形はこのような伝統と技術を受け継ぎながら、
その時代の流れ、風俗や好みを反映した形を追求して今日に至ったものだそうです。
かつては他の素材の人形とともに、京人形という総称の中に含まれていましたが、昭和32年に「京陶人形」と命名されました。
多品種、少量生産が主体なので、作られている形は多様です。子供たちのすこやかな成長を願う雛人形や五月の節句もの、
歴史をたどる時代風俗、特に王朝文化を題材にした優雅な時代もの、御所人形をはじめ幼児の愛らしさで表現する童子もの、
歳守の干支などの動物もの、素材そのものを活かした素朴なもの、抽象的でモダンなもの、また独自の技法で作られている土鈴は、
音色、形、彩色ともに豊かで人気があります。
京陶人形工芸協同組合の方々は、「これからも、人々の心をなごませる人形や、時代と向きあったユニークな人形を生みだしたい」と
日々、製作に励んでおられます。
皆様の新春に、あなただけの「幸せを呼ぶ形」を選んでいただければ幸いです。

多種多様な釉薬によって彩られた、きれいで、日常に使いたくなる器…それが守崎正洋氏の作品です。
鮮やかな紅紫の辰砂、さわやかな水色の鈞窯、多様な天目系の釉薬はそれぞれ黒さが違います。
守崎氏の多様なカラーバリエーションといろいろな形の器は、補充してもすぐに売り切れになる会館でも人気の作品です。
そんな作品をいつも以上にずらりと並べてみていただける展覧会は、楽しい企画となることでしょう。
たくさんの中からお気に入りを見つけていただくチャンスです。皆様のご来場をお待ちしております。
<守崎正洋 陶歴>
1971年10月19日 京都市生まれ
1999年 京都伝統工芸専門校(現在 大学校)陶芸本科修了
1999年 以後二年間、大覚寺陶房にて和泉良法氏に師事
2002年 (株)たち吉主催『京都陶芸の新しい芽』入選
2003年 京都市工業試験場陶磁器コース専修科修了
2003年 京都、嵯峨野にて開窯 独立
2004年 伝統産業「京の若手職人」海外(イタリア)派遣事業に選出
2006年 2006『めし碗グランプリ展』入選
2008年 第26回『朝日現代クラフト展』入選
2012年 第10回『ローディ陶器コンクール』(イタリア)入賞
〒616‐8314
京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町16-22
TEL&FAX:075-872-3543(工房)