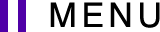山本たろうさんは「鎬(しのぎ)紋」の加飾と、やさしい色調のトルコブルーの釉薬が特徴の作家です。
鎬紋とは、生地をヘラなどで削って溝を彫り、稜線を作る加飾技法で、その稜線を刀の「鎬」に見立てたものです。 トルコブルーの銅釉は透明度が比較的高く、かつ分厚く掛けるので、鎬紋の凹凸に沿って釉薬の厚みが変わり、豊かなグラデーションが現れます。
シャープな鎬紋の生地がやさしい色調のトルコ釉を纏った姿は、春霞の中に佇むビルのようです。 浮かれ出でたくなる季節、「青い春」をご覧にお出かけ下さいませ。
山本たろう 陶歴
1974年 京都府に生まれる
1994年 京都府立陶工高等技術専門校 卒業
1997年 京都市工業試験場 陶磁器コース 卒業
1999年 大阪美術専門学校 陶芸科 卒業
沖縄県読谷村 北窯にて修業
2001年 宇治市炭山にて作陶

嵯峨美術大学(旧称:京都嵯峨芸術大学/2017年4月より校名変更)は京都の嵐山に立地する芸術系大学です。桂川の畔の閑静なキャンパスでの少人数教育という大変恵まれた環境で、学生の方々は日々熱心に制作をされています。
本展では、現在陶芸工房で制作する5名の学生たちが、今年度の集大成として取り組んだ、進級作品を一堂に展覧いたします。展覧会名の「いまいの」とは、学生の提案によるもので、「今」と「イノベーション」を掛け合わせた造語です。若いエネルギーに満ち溢れた作品、今を生きる学生たちのイノベーションを是非ご高覧くださいませ。
参加学生
・近藤翔太 (3回生)
・柴田暢也 (3回生)
・前羽りお (3回生)
・上原真衣 (2回生)
・西野由希 (2回生)

中村亮平さんの器は、使いやすい端正なデザインでありながら、手づくりの温かみが豊かに感じられます。 その魅力は茶陶制作で学ばれた「用の美」の意識と技術に裏打ちされたものです。
中村さんは「普段使いでありながら、日々の生活が少しでも潤うような器」を目指されていますが、それは日常に寄り添う「普段使い」だからこそ可能ではないのでしょうか。
ちょうど東山花灯路で春を迎えるころ、あなたの暮らしを照らす逸品を、新たな門出を迎えられる方へのプレゼントなどを、探しにお越しくださいませ。
中村亮平 陶歴
1981年 京都に生まれる
1999年 京都市立銅駝美術工芸高等学校 陶芸専攻 卒業
2001年 嵯峨美術短期大学 陶芸コース 卒業
2002年 京都府陶工技術専門学校 成形科 卒業
2003年 京都府陶工技術専門学校 研究科 卒業
京都山科にて中村秋峰に師事
2014年~京都市立芸術大学 非常勤講師

香港理工大学の学生による器のデザインを京都の作家が制作するという、プロジェクト展示です。
香港の日常生活では陶磁器の食器は馴染みがなく、あまり使用されません。それに対して日本は日常的に陶磁器が使われる、いわば「やきもの大国」です。そのような文化的背景に着目し、「香港の日常に陶磁器を。」という考えのもとに香港のデザインの名門校である、香港理工大学の学生が器をデザインし、京都の作家が制作をして、両国で発表する企画です。
まさに、異文化交流から生まれる新しい陶磁器の形をご覧ください。
※香港展を2018年3月末日、香港理工大学内にて開催予定。
黒川正樹 陶歴
1977年 名古屋市に生まれる
2000年 アジア〜アフリカをひとり旅する
2002年 名古屋市立大学 経済学部卒
2006年 京都府立陶工高等専門校 成形科 修了
信楽 雲井窯に入社
2013年 雲井窯退社 京都山科にて独立
山口直人 陶歴
1972年 北海道に生まれる 西神戸育ち
2008年 京都伝統工芸大学校卒業 滋賀県草津に移り住む
2009年 京都東山にて作陶
2011年 京都山科に工房移転

横山工房は、染付、結晶釉、練り込みの技術を有し、とりわけ鉄釉・天目釉に関して高い知識と技術を持たれ、後進の育成にも力を入れられています。その油滴天目は、落ち着いた色調が特徴的です。茶碗や酒器などの制作はもちろん、山椒魚の箸置きなども可愛らしく、鉄釉の新たな一面が垣間見えます。
本展では茶碗、酒器、茶器、小物など、鉄釉が施された様々な作品を展覧いたします。お気に入りの逸品を探しに「鉄釉の世界」をお楽しみください。
横山工房(横山真理子・直範)
1980年 京都東山に横山工房「真窯」を 開窯
横山真理子 陶歴
京都工芸美術作家協会作家協会会員 日本伝統工芸会準会員
1976年 嵯峨美術短期大学 専攻科卒業
(岩淵重哉氏,東憲氏、近藤潤氏、大西政太郎氏に師事)
1979年 京展 新匠工芸会展 90明日への茶道美術公募展 入選
女流陶芸展 新人賞受賞
2007年~日本伝統工芸近畿支部展 日本伝統工芸展 入選、
2016年 日本伝統工芸近畿支部展 京都新聞賞受賞
横山直範 陶歴
元京都市産業技術研究所研究部長 京都美術工芸大学特任教授
京都市立芸術大学非常勤講師 独)京都市産業技術研究所講師
東洋陶磁学会会員 日本伝統文化学会会員
1980年 信州大学大学院工学系研究科修士課程(ガラス工学,粘土工学)修了
1981年 京都府立陶工職業訓練校(図案科)卒業
1980~1989年
昭和製陶株式会社 勤務 (彫塑家 船津英治氏、陶芸家 加藤庄氏に師事)
1989年~2014年
京都市産業技術研究所 勤務
陶磁器技術(釉薬・素地・焼成)研究に従事
2014年~京都美術工芸大学 勤務

平井さんは、有機的なフォルムに沿って線状の加飾が施された、端正な造形を制作されます。
この線状の加飾は「彩紋積層」と呼ばれ地層のイメージからつくられたものです。 奈良県の唐古・鍵遺跡からほど近い場所に工房を構える彼は、風化した遺跡からの出土品と、自身の心の奥底の記憶との間にかすかな共通点を感じ、その感覚を具現化しようと制作されています。また、それを見た人の感覚が、彼自身の抱くかすかな記憶の感覚と共鳴すれば、と考えておられます。
本展では、オブジェを中心に器なども展覧いたします。あなたの「記憶の層」を辿りながらご覧になってはいかがでしょうか。
平井明 陶歴
1975年 奈良市に生まれる
1994年 京都府立陶工高等技術専門校 卒業
宇治 朝日焼にて修行(2000年まで)
2000年 唐古・鍵遺跡のある奈良県田原本町にて独立
2006年 日本伝統工芸近畿展「新人奨励賞」(以降 毎年入選)
「日本経済新聞社賞」(2013年)
「奈良県教育委員会教育長賞」(2015年)
「日本工芸会賞」(2016年)
2011年 日本伝統工芸展 入選
(以降 2014~2018年 毎年入選)
2015年 陶美展 入選
「茨城交通賞(優秀賞)」(2016年)
現在 日本工芸会 正会員

京都陶磁器協会は、作家・窯元・原料販売所等の有志の集まりによって構成される団体で、その中には電磁紡織器部という部会が存在しています。
この電磁紡織器とは、清水焼の関連産業として明治20年前後に、碍子製造より始まり、明治期末には水力発電開始事業の活発化に伴い、電気機器用の陶磁器を製造し始めました。
明治39年には松風嘉定が松風陶器合資会社を設立し、京都陶磁器試験場長 藤江永考、京都大学教授工学博士 小木虎次郎などの援助により、普通高圧碍子の研究に成功、
ついで特別高圧碍子を製造し始めました。
これにより、京都の電磁器製造は一躍名声を博し、海外輸出を行うまで成長しました。
この成功に刺激され、他産地でも一般の陶磁器製造から転業・兼業する者が現れましたが、京都は群を抜く高品質でした。
大正期に入り、第一次世界大戦による内需の拡大に伴い、電磁器の需要は大きく高まり、京都の陶磁器業界における影響力も大きくなっていきました。
第二次世界大戦下においては、京都陶磁器統制組合が設立され、原料や燃料、又、それらの運搬などの配給を行う組合にも、多くの電磁器製造業者が参加し、高級品が否定され多くの作家・窯元が苦しんでいた、京焼の暗黒期を支えてきました。
弊協会は、旧統制組合の資産を母体とし、京都の陶磁器業界の普及進行のための事業を行う為、昭和28年に設立されたもので、その構成員として電磁器紡織器を製造する者が加入している、全国でも稀有な陶磁器関連団体です。
古くは明治期より、京焼と共にあった電磁紡織器ですが、現在は、「京都」や「京焼」とのイメージから離れてしまっています。
そこで、本展では京都より発信されている、隠れた京焼として紹介し、現代を生きる焼き物の知られざる姿をご覧いただければ幸いです。

竹村さんは天然の植物灰を調合した釉薬で、様々な色彩と表情を生み出します。
灰釉の歴史は古く、現代においても多くの作家が研究を行っていますが、竹村さんはヒマワリやブドウ、イチジクなど一般的には用いられない植物を燃やして灰を作り、
それを調合して独自の色彩を生み出します。掲載写真の作品はヒマワリの灰釉が掛けられていますが、不思議と花と同じ黄色に発色しています。
本展では、色とりどりの灰釉をまとった壺や食器など、様々な器を展覧いたします。
それぞれの色がどんな植物の灰から生まれた色なのか、想像しながらご覧になるのも楽しいのではないでしょうか。
〈竹村繁男 陶歴〉
1953年 京都山科に生まれる
1972年 京都市立日吉ヶ丘高校陶芸科卒業 木村盛伸先生に師事する
1975年 第四回『日本工芸会近畿支部展』初入選 以来毎年入選
1980年 独立し、山科に大日窯を開窯する
1988年 第三十五回『日本伝統工芸展』入選
1989年 『土の子会』結成
1996年 第二十五回『日本伝統工芸近畿
展』奨励賞受賞
1998年 第五十三回『新匠工芸会展』入選
2007年 第三十六回『日本伝統工芸近畿展』
京都府教育委員会教育長賞受賞
2008年 日本工芸会陶芸部会正会員による、
第三十六回『新作陶芸展』日本工
芸会賞受賞
2010年 第三十九回日本伝統工芸近畿展に
て鑑査委員に就任
日本工芸会正会員
京都府美術工芸作家協会会員

市岡さんは極めて高いロクロ成形の技術で喫茶道具を制作されます。
その中でもとりわけ急須は、小さいパーツの接合やバランスなど難しい点が多い道具です。
市岡さんの急須を見ると、その精緻な仕事から、幕末の京焼三大名工といわれる青木木米の仕事を思い起こします。
磁器の極めて薄い急須を、ロクロで挽くことができる陶工は、今となっては稀有な存在です。
市岡さんは「家にあると、心が豊かになる」そんな作品を目指しながら毎日作陶されています。
本展では、今様喫茶道具を展覧いたします。皆様と喫茶道具のこころ豊かな出会いを願います。
〈 市岡和憲 陶歴 〉
1989 村田亀水に師事する
1996 独立 現在に至る
2007 技術参考作品(急須)を京都市が買い上げる
2010 第39回日本伝統工芸近畿展(急須)入選
以降、第40・41・44回展入選
2012 第26回日本煎茶工芸展入選
2013 単室薪窯築窯
2015 第62回日本伝統工芸展(急須)入選