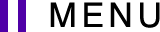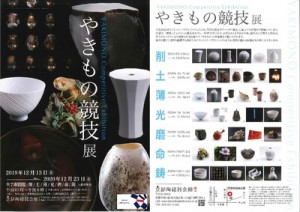木田陽子さんは日本語の文字から着想を得て作品を生み出します。
美しい文字は的確な線と余白により構成されるものです。
彼女の作品もまた、線と面が織り成す美しい空間を内包しています。彼女はしばしば、個々の作品が持つ空間を共鳴させ、鑑賞者と作品群との心理的距離を近づけることを試みます。その空間は、まさに文字で紡がれた物語のように鑑賞者の感覚にはたらきかけ、その世界観へといざないます。
本展では弊館にどのような空間が生み出されるか、期待の新進作家の世界をお楽しみ下さいませ。
木田陽子 (きだ・ようこ) 陶歴
1996年 兵庫県生まれ
2020年 京都市立芸術大学 陶磁器専攻 卒業
現在 同大学 大学院修士課程 在学中
2019年 「わん・ONE・碗」優秀賞
2020年 「京都市立芸術大学作品展」同窓会賞
「アートアワードトーキョー 丸の内 2020」審査員 建畠晢賞・審査員 長谷川新賞
2021年 「群馬青年ビエンナーレ」入選
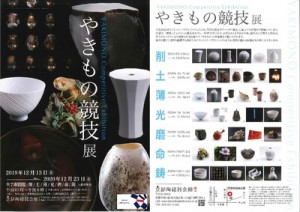
新型コロナウイルスの感染防止を目的とした臨時閉館に伴い、2020年6月より延期しておりました展覧会を開催させていただきます。
東京2020オリンピック・パラリンピックにちなみ、陶芸の技法やテーマを競技に見立てた「やきもの競技展」を開催いたします。本展は、「競技」ごとに7つの展覧会をリレー形式で行います。
4つ目の競技は「磨」です。やきものは、表面を研磨することにより耐水・防汚性や強度が増すことから、古来より各地で様々な「磨く」技法が発展しました。また、そのような実用性だけでなく、しっとりとした美しい光沢は加飾技法としても捉えられています。本展では、伝統的な朱泥茶器、イタリアのテラシジラータから、造形作品まで、様々な作品を展覧いたします。
競技を通して、選手も鑑賞者も熱狂するオリンピック・パラリンピックのような、熱気に溢れる展覧会をお楽しみ下さいませ。
出展者(五十音順)
秋山陽 Yo Akiyama (京都)
鯉江廣 Hiroshi Koie (愛知)
重松あゆみ Ayumi Shigematsu (兵庫)
Leonardo Bartolini レオナルド・バルトリーニ (イタリア出身・熊本)
Marcello Pucci マルチェッロ・プッチ(イタリア)

昨年からのコロナ禍により仕事や生活が変わり、私自身もこの多くの時間を、そして陶芸の根幹である土を見つめ直しました。地元亀岡にて、裏山や出先で隆起した地層を見ればサンプリングし、幾度も試験した結果、新しい風合いに出会うことができました。この模索の結果を今回の新作として展示します。
また定番オリジナルの黒釉流しや、白釉ベースの新作なども見て頂けますと幸いです。
これらの器が、家での食事をより楽しむ時間が増えたこの機会に、皆様の素敵な瞬間の黒子となればと想っております。
森本真二(もりもと・しんじ)
1963 京都に生まれる
1987 京都府陶工職業訓練校成形科修了
1992 京都市、清水焼団地に新工房を開く
国際陶磁器展 美濃’92初入選
1998 工房を亀岡・東別院の地へ移す
2015 銀座松屋にて20回目の記念個展開催
赤織部と天目、穴窯焼成を中心に現在に至る。

新型コロナウイルスの感染防止を目的とした臨時閉館に伴い、2020年より延期しておりました展覧会を開催させていただきます。
木村巳奈子さんの作品は、使いやすく落ち着いたおしゃれな器です。
たとえば、木村さんの作る急須は手がやや大きく感じますが、手になじみやすい大きさに作られています。また、蓋を開けてみると茶漉しなども丁寧に作り込まれています。手に取ることにより、使うことにより、さらに魅力が感じられる器です。
本展では、赤絵、鉄絵、染付など様々な急須などの茶器を中心に展覧いたします。
生活の中になじむ「いつものうつわ」をお手に取ってご覧くださいませ。
木村巳奈子(きむら・みなこ)陶歴
1994年 京都精華大学 陶芸専攻 卒業
個展・グループ展
ギャラリーにしかわ 京都(2008、‘10‛ 13 ‛16 ‛18)
ギャラリーCENTINNIAL/MANIFESTO GALLERY 大阪(2010、‛15 ‛18 ‛19)
一保堂茶舗 京都・東京(2013、‛16)
ギャラリーESPACE名古屋・ESPACE KYOTO(2015、‛17)

これまで多くの人間国宝を輩出してきた日本工芸会近畿支部が運営、開催する日本伝統工芸近畿展が今年50回の節目を迎えます。
それを記念して、現在支部運営に携わる役員による選抜展を企画いたしました。
多くの産地を抱え、多彩な技法、表現による近畿支部陶芸部会の今を感じて頂ける展覧会です。
また設立、運営を担って来られた重要無形文化財保持者(人間国宝)の石黒宗麿、富本憲吉、近藤悠三、清水卯一の作品も展示いたします。
ご高覧、ご批評頂きますようお願いいたします。
近畿支部陶芸部会長 岡田優
出品者 五十音順
猪飼 祐一
石橋 裕史
岡田 優
加藤 清和
神崎 秀策
國定 克彦
清水 一二
神農 巌
樋口 邦春
古川 拓郎
本多 亜弥

【お知らせ】
新型コロナウイルスの感染防止の観点より、誠に申し訳ございませんが、2022年に開催を延期させていただきます。なお延期日につきましては、後日改めてご案内させていただきます。
どうぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
田中大輝さんは、使う人や料理に寄り添ううつわ作りに重きを置いて、京都京北にて日々制作しています。
型が織りなす美を求め、様々な技法や釉薬の調合、図案に渾身をそそいでいます。
本展は「人となり」ならぬ「うつわとなり」をテーマとし、うつわの性質や有様を感じていただけるように設えています。 粉引や染付、白磁など、幅広いニーズに応えるため、こだわりを持って 作りあげられた作品が並びます。
ぜひご高覧ください。
田中大輝(たなか・だいき)
1990生
2012京都精華大学芸術学部素材表現学科陶芸コース卒業
2012村田製陶所に勤務 村田 森 氏に師事
2015右京区京北にて独立

【お知らせ】
新型コロナウイルスの感染防止の観点より、誠に申し訳ございませんが、2022年に開催を延期させていただきます。なお延期日につきましては、後日改めてご案内させていただきます。
どうぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
谷口晋也さんは、近年茶具の制作に力を注がれています。
お茶にまつわる器は、茶道具や煎茶器などをはじめ、様々なものがありますが、本展では、土瓶をはじめ注ぐ器を中心に様々な茶具を一堂に展覧いたします。
谷口さんは、今日では使われる機会が少なくなった土瓶に特に強い興味をもたれ、制作されました。やさしい質感の本体に付けられた取手も彼の手作りです。いろいろな茶具の垣根を越える谷口さんの世界をお楽しみくださいませ。
谷口晋也(たにぐち・しんや)陶歴
1978 京都生まれ
2003 京都市立芸術大学大学院工芸専攻陶磁器修了
日常食器や茶具、水の造形と宇宙をテーマにした立体造形などを中心に「ものつくり」として活動。

新型コロナウイルスの感染防止を目的とした臨時閉館に伴い、2020年より延期しておりました展覧会を開催させていただきます。
八木美詠子さんの作品は、淡い雰囲気を纏ったかわいらしい器です。
しっとりとした釉薬は八木さんがご自身で研究されたもので、そこにやさしい色調の染付や色絵を施されます。
本展では、季節に合わせて桜の絵柄の食器を中心に展覧いたします。淡い雰囲気にぴったりの桜の絵柄を纏った器たちがならぶ情景は、まさに花霞のように私たちを楽しませてくれるでしょう。
ぜひ、お手に取ってお気に入りの逸品をお探しくださいませ。
八木美詠子(やぎ・みえこ)陶歴
1973 京都生まれ
1996 奈良教育大学 美術専攻 卒業
2002 陶工高等技術専門校 図案科修了
楽峰製陶所 勤務
2011 京都市産業技術研究所 伝統産業技術者研修 陶磁器コース本科修了
2013~ 同コース 非常勤講師
東山区に開窯

毛利愛実子さんの家の裏には、深い山が広がっています。
家の隣の原っぱは、耕すことで畑になります。家の周りには、土や雪の上に残された生き物の気配があちらこちらにあります。
自身の生活から姿の見えない彼らの生活を想像し、また、自身のつくったものから彼らのつくるものを想像します。
本展は、作家の日々の生活と、姿の見えない何かの存在が垣間見える展示となります。ぜひご高覧下さい。
1993年 大阪生まれ
京都市立芸術大学工芸科に入学し、
陶磁器を専攻する。
同大学の大学院卒業後、2020年鳥取県湯梨浜町に移住し、生活をはじめる。

新型コロナウイルスの感染防止を目的とした臨時閉館に伴い、2020年より延期しておりました展覧会を開催させていただきます。
生まれ育った京都の嵯峨野に工房を構え、作陶する守崎正洋氏。
ご自身も生活の中で料理をすることで、ひとびとが共有する時間に映える事を自然と意識し、うつわや酒器を製作している。自然と装飾のないフォルムにつながり、そこには使われることで生きる心地よい余白が見える。
うつわ本来の使命を兼ね備えた、あくまでも料理やお酒を引き立たせる控えめな加色でありながら、天目も含む豊富な色の展開。春を迎えるこの時期にふさわしい桜華釉も含め、色とりどりの食器たちが空間を彩る。
守崎正洋(もりさき・まさひろ)陶歴
1971年10月19日 京都市生まれ
1999年 京都伝統工芸専門校(現在 大学校)陶芸本科修了
1999年 以後二年間、大覚寺陶房にて和泉良法氏に師事
2002年 (株)たち吉主催『京都陶芸の新しい芽』入選
2003年 京都市工業試験場陶磁器コース専修科修了
2003年 京都、嵯峨野にて開窯 独立
2004年 伝統産業「京の若手職人」海外(イタリア)派遣事業に選出
2006年 2006『めし碗グランプリ展』入選
2008年 第26回『朝日現代クラフト展』入選
2012年 第10回『ローディ陶器コンクール』(イタリア)入賞